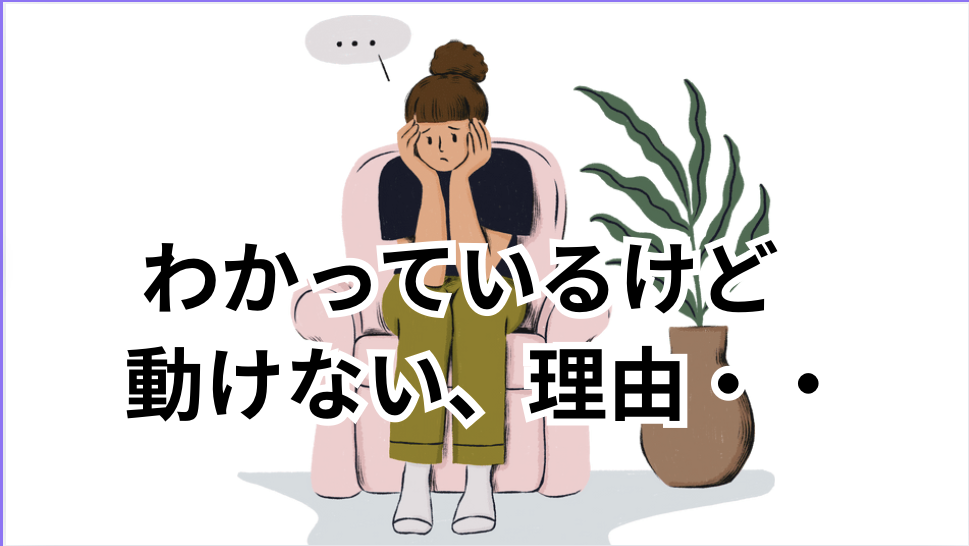「わかっているのに動けない」の正体 — 知識の定着を邪魔する“思考の渋滞”とは?
知識は増えたのに、なぜか動けない——。
それは「思考の渋滞」が起きているサインかもしれません。
停滞を抜けるためのマインド整理法をお伝えします。
「頭ではわかっているのに、できないんです」
マインドセットを長く学んでいる人から、よく聞く言葉です。
脱力でも、思考でも、学びの中でこの壁にぶつかるのは、実は“停滞”ではなく「成長の通過点」。
ただ、その正体を知らないまま抜け出そうとすると、どんどん渋滞がひどくなってしまうのです。
今日は、その“思考の渋滞”をほどくヒントをお伝えします。
■「知っている」ことが増えるほど、動けなくなる paradox
学び始めたころは、何も知らないぶん行動が早い。
「とりあえずやってみよう!」と、軽やかに動けたはずです。
ところが、知識が増え、理論がわかってくると──
「これって、あの理論的に合ってるのかな?」
「前に先生が言っていたことと違う気もする…」
そんなふうに、頭の中で交通整理が始まります。
そして気づけば、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態に。
結果、「わかっているのに動けない」というブレーキがかかるのです。
■“思考の渋滞”が起こるタイミング
マインド的に見ると、この状態は“知識の整理が追いつかない時期”に起こります。
脳の中では、
「新しい考え方」
「今までのやり方」
「人から学んだ理論」
「自分の体験」
…これらが一斉に交差して、優先順位を決められずにいるのです。
たとえるなら、交差点の信号が全部青になってしまったような状態。
どの方向も「正しい」からこそ、どの道に進むべきか分からなくなる。
でもこれは、“混乱しているからダメ”なのではなく、
**「次のステージへ進む前の自然な整理期間」**なんです。
■「実践でしか整理できない」領域がある
ここで多くの人がやってしまうのが、
「もっと理解しよう」と、さらに知識を積み上げること。
でも、頭で整理しようとすればするほど、渋滞は悪化します。
なぜなら、“思考の渋滞”は「頭で考えても解けない渋滞」だからです。
たとえば脱力の練習でも、
「肩の力を抜こう」「重心を感じよう」と考えすぎると、逆に力が入ってしまう。
本当に必要なのは、「まずやってみて体で感じること」。
思考の渋滞を抜ける鍵も同じです。
動きながら、整理されていく。
これがいちばん自然で、いちばん早い方法なんです。
■「わかっているのに動けない」を抜ける3つのステップ
1️⃣ 小さく動く(考えすぎない)
完璧を目指すほど動けなくなる。
「これでいいのかな?」と思いながらでも、一歩動く。
動けば必ず何かが見える。
2️⃣ 感じたことを書き留める
行動したあとに、「どう感じたか」を記録する。
これが思考の交通整理になります。
言語化は“頭の中の整理術”です。
3️⃣ 考えを寝かせる(無理に答えを出さない)
渋滞中は、焦って正解を出そうとしがち。
でも、整理が進むには“時間”が必要。
静かな時間こそ、学びが定着する大切な期間です。
■「考える」を超えて、「感じる」へ
思考の渋滞を抜けると、「考えなくても動ける」段階がやってきます。
これは“無意識レベルに落とし込まれた理解”で、いわば学びの統合です。
たとえば、ピアノで“脱力の感覚”を体で覚えた人は、
もう「力を抜こう」と考えなくても、自然に脱力できる。
同じように、マインドも体に馴染むと、行動に自然さが戻ります。
■さいごに:「動けない時期」は、成長の準備期間
“思考の渋滞”が起きるのは、それだけ学びが深くなった証。
何も知らなかった頃には、渋滞すら起きなかったはずです。
だから、もし今「動けない」と感じているなら、
それは「次のステージへ行くためのアップデート中」なんです。
焦らず、比べず、
今日できる小さな一歩を。
動けば、また流れ始めます。
それが“わかっているのに動けない”を抜ける、いちばん自然な方法です。